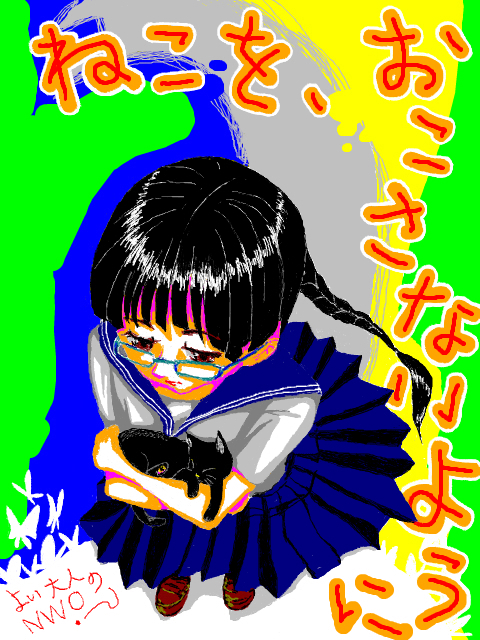温泉とサウナと漫画喫茶が複合したような施設で、二階堂地獄ゴルフを6巻まで読む。例によって、エスエヌエスで1話が話題になっていたのを思い出したからですが、結論から言うと、男性作家の悪い部分の煮こごりみたいな作品でした。直近に、メダリストやダイヤモンドの功罪などの良質な少女漫画を経由したせいもありますが、すべての男性が多かれ少なかれ持っている異性への偏見(性的な)と、昭和の倫理観を令和にアップデートしようとして大失敗した臭気が、全編にわたってただよっているのです。なぜか「欧州における香水文化の発展は、下水道の整備が不充分なことによる、不衛生に起因するものであった」みたいな一節がアタマをよぎりましたね。本作の感想を述べるにあたり、福本作品との個人的な接触履歴をまず開陳しておくならば、天を全巻読破し、アカギの6巻までと最終話だけを読み、カイジは第1部終了までを追いかけて、以後は疎遠になったぐらいの不熱心なファンです。天の最終章を下敷きにしたパロディを書いたこともあるので、けっしてキライな作家ではないのですが、麻雀漫画のオススメに福本作品を挙げないことからも、小鳥猊下の感じている距離感は、みなさんに伝わっているかと思います。西原理恵子だったかが、彼の漫画群を評した「まちがった算数の計算式による頭脳戦」みたいな表現は、じつに正鵠を得ていて、摩訶不思議に私淑するファンの多いアカギにしたところで、「配牌とツモがいいことを前提にした、ご都合主義の奇矯な戦術披露」以上の感想は出てきません。もし漫画の神様(not手塚治虫)が、この寒風ふきすさぶ四畳半に現れて、仮に「1つの完結した作品を漫画史から消滅させることを代償に、1つの打ち切り作品を完結まで連載させてやろう」との申し出があったとすれば、秒でアカギを歴史から抹消して、度胸星を再開させますからね!
いまゴールデンカムイの作者が、打ち切りになったアイスホッケー漫画のリベンジ・リメイクをしているように、近年の福本伸行は”熱いぜ辺ちゃん”あたりまでの「売れなかった人情モノ路線」へ再チャレンジしているように見えるし、アカギの娘?が主人公の新作ぐらいから、「これまで避けてきた女性キャラの描写をキチンとする」ことを創作の裏テーマとしているように思います。この2項目を補助線として引くと、二階堂地獄ゴルフという作品をより深く理解できるのではないかと考えながら、読みはじめました。さすが売れっ子の人気作家だけあって、物語の設定と序盤のビルドアップだけで、グイグイと読み手を引きこんでいきます。3巻までは近年の同氏の作品と比べて、ストーリー展開のテンポも早く、「これは、新境地を期待していいのかも?」とさえ感じていたのが、4巻冒頭から突如として「まちがった算数の計算式」によるトンデモ頭脳戦がはじまり、6巻を読み終えるころにはすっかり、男性作家による悪いストーリーテリングの総天然色見本ーーキャラはブレブレで一貫性がなく、ストーリー展開はその場その場の思いつきーーであるところの「いつもの福本漫画」へと印象は落ち着きました(続きを手にとることは、もうないという意味です)。二階堂地獄ゴルフのストーリーをメダリストで例えるなら、「バッジテストに落ち続け、司先生は選手に復帰して去り、18歳をひとりでむかえた結束いのりの話」であり、ダイヤモンドの功罪で例えるなら、「少年野球の監督に車内で肛門性交を強要され、トラウマで野球ができなくなった綾瀬川次郎の話」であり、本質的に「時間と紙幅を費やしまで、わざわざ語る必要のない話」になっているのです。なぜって、そんなみじめな話は、われわれ凡人の生きている現実そのままで、虚構の称揚ぬきで物語にする価値なんて、微塵もないからですよ!
たしかに、漫画家として売れるまでの苦労はあったのかもしれませんが、いまや国民的な人気作家となり、横になっているだけで印税と利子で大金が転がりこんで(銀と金!)くる、現世での大成功を収めたイケメンなのですから、わざわざ社会の掃きだめに巣くう醜い容姿の男性をとりあげ、いたずらに不幸にさせる漫画ばかりを執筆するのは、札束の盾に守られた安全圏から”鉄骨渡り”の愉悦を味わうためでないとすれば、マゾヒスティックな性癖に由来した不謹慎きわまる執拗のいじめ行為にしか、もはや見えないのです。もう還暦をとうにすぎていらっしゃるでしょうから、そろそろ連載中の作品はすべてテキトーにーーだれも続きを待ちわびていないのでーー終わらせて、新人賞を受賞したあとの長い下積み時代からはじまり、麻雀誌で「バブル時代と寝た」あと、一般漫画での大ヒットへといたる、福本版アオイホノオに着手する人生の季節ではないでしょうか。そのほうが現状よりも、よっぽど作者と読者の双方にとってウィンウィンになると思いますよ! あと、温泉とサウナと温泉喫茶が複合したような施設に置かれていた二階堂地獄ゴルフの単行本ですが、3巻までは読まれすぎて分解しそうなほどメロメロになっているのに対して、4巻以降はほぼサラピンの状態で「た、大衆から虚構に向けられた批判の、アナログによる表現形式……!!」となりました(キライな表現)。